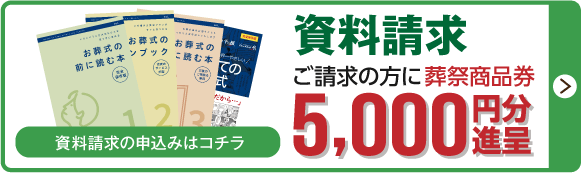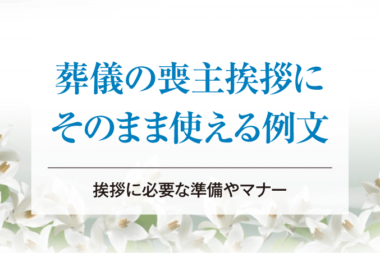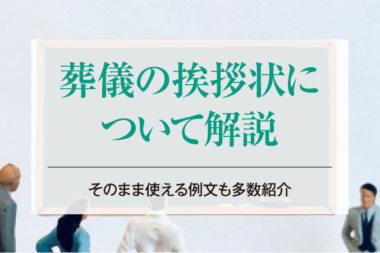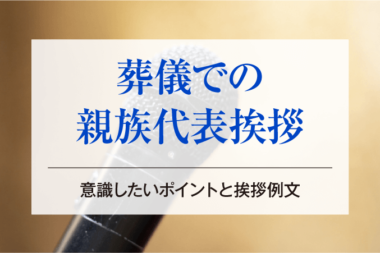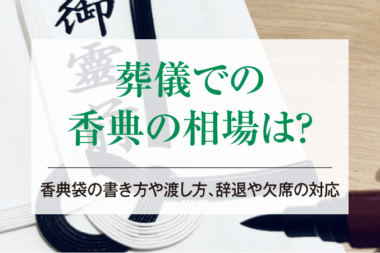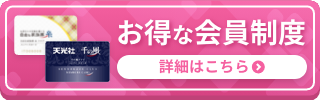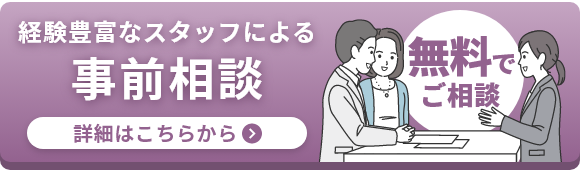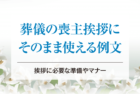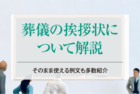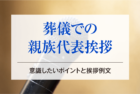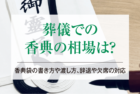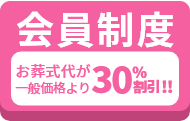お葬式の豆知識葬儀、法事、終活など様々な疑問に対する解決策や
マナーについてのお役立ち情報をお届けします。
葬儀でのお悔やみの挨拶・言葉|基本マナーや状況別のメール文例
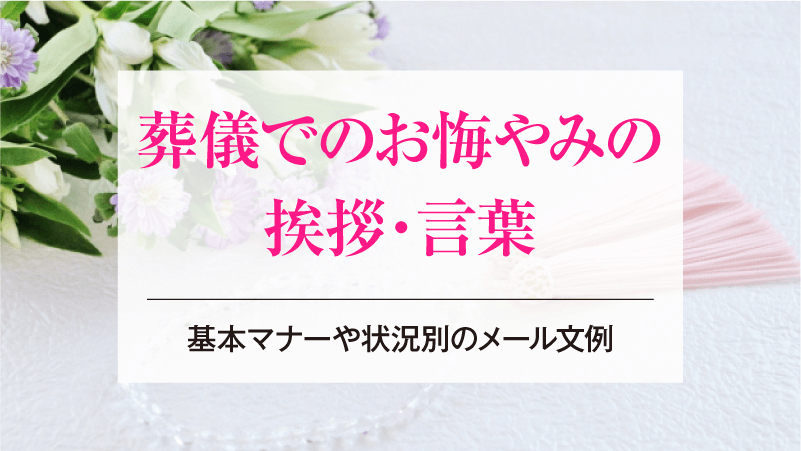
葬儀の際にご遺族に伝えるお悔やみの言葉は、親族を失ったご遺族に対する思いやりを込めた言葉です。しかし、思いが込められていればどのような挨拶でも問題ないわけではなく、お悔やみの言葉には基本的なマナーが存在しています。
本記事では、葬儀でのお悔やみの挨拶について、基本的なマナーや状況別の文例を紹介します。
\ お葬式の事が気になりはじめたら /
目次
お悔やみの挨拶の基本的なマナー

お悔やみの挨拶の基本的なマナーは以下の5つです。
- それぞれ詳しく解説していきます。
①短く簡潔に伝える
お悔やみの挨拶は、短く簡潔に伝えるようにしましょう。ご遺族、特に喪主は多くの弔問客に対応しなければならないため、挨拶に時間をかけすぎるのはよくありません。また、無理に長く話そうとすると余計な言葉をかけてしまい、かえって差し障りが生じることもあるでしょう。親族を失ったご遺族は深い悲しみに包まれているため、何気ない言葉によって心がさらに傷ついてしまうことも考えられます。
故人と深い親交があった場合はいろいろなことを話したくなってしまうかもしれませんが、ご遺族の負担を増やさないよう配慮するべきです。
②安易な励ましの言葉を使わない
「元気を出してください」「頑張ってください」などの安易な励ましの言葉は使わないようにしましょう。親族を失った悲しみから立ち直るのは簡単ではないため、安易な励ましは逆効果です。
ご遺族は参列者に挨拶するだけでも相当の気力を使っているため、励ましの言葉をかけるのであれば、ある程度期間を空けてからにしましょう。
③死因などを詳しく尋ねない
なぜ亡くなったのかを聞かされていない場合、死因が気になることもあるかと思いますが、ご遺族に死因を聞くことはマナー違反とされています。事故や病気が死因だった場合、ご遺族がそのときの状況をなるべく話したくないということも考えられるため、詮索は控えるようにしてください。
また、ご遺族だけでなく、他の参列者に死因を尋ねるのもマナー違反となります。葬儀の場では故人の死因について語ることは絶対に避け、ご遺族の心に寄り添う気持ちを伝えるだけにとどめておきましょう。
④重ね言葉・忌み言葉の使用を避ける
「いろいろ」「ますます」などの重ね言葉や、「死ぬ」「消える」などの不幸や死を連想させる忌み言葉は使わないようにしましょう。重ね言葉は一見、使用することに何も問題がないように感じますが、不幸が「重なる」「繰り返す」といった意味で捉えられてしまうため、使うべきではないのです。
また、参列者側が使ってはいけない言葉として「大往生」があります。高齢の方が亡くなった際に用いられる言葉ですが、大往生はご遺族側が使う言葉なので参列者側が使うのはマナー違反です。大往生は「苦しむことなく、安らかに死を迎える」という意味があるため、もっと長生きしてほしかったであろうご遺族側にかける言葉としては不適切なのです。
普段の生活では何気なく使っている言葉が重ね言葉や忌み言葉となっている場合があるため、葬儀の際は十分に注意しましょう。
⑤無理に言葉をかける必要はない状況もある
お悔やみの挨拶は、状況によっては必要がない場合もあります。挨拶をするタイミングを失ってしまい、式の進行を妨げてしまう可能性がある場合は、無理に言葉をかけなくても大丈夫です。挨拶がなくとも、お焼香や黙とうによって故人様を悼む気持ちはご遺族に十分伝わります。
| 葬儀の供花については以下の記事で詳しく解説しております。 供花とは?葬儀に手配する方法や流れ、マナーや注意点、値段の相場 |
よく使われるお悔やみの挨拶
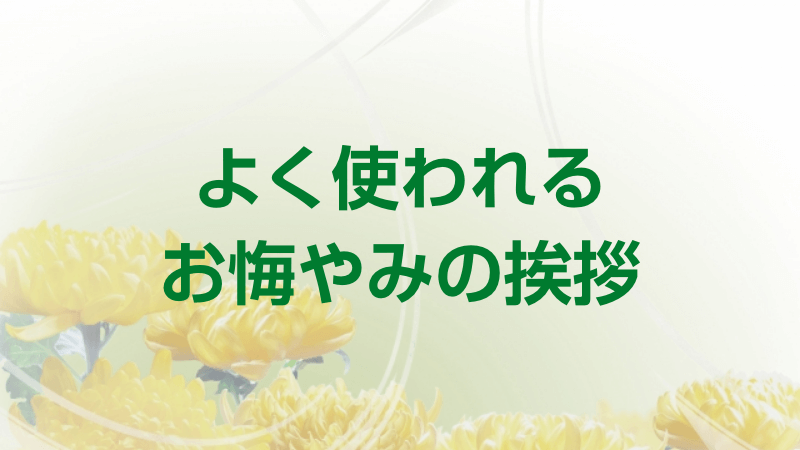
お悔やみの挨拶でよく使われる言葉は「お悔やみ申し上げます」と「ご愁傷様です」の2つです。
それぞれの挨拶にはどのような意味が込められているのか、文例とともに見ていきましょう。
お悔やみ申し上げます
故人様の死を悲しみ、弔う思いを伝えるための言葉です。口頭で伝えるときだけでなく、弔電の文中にも使用できます。実際に使用する際は「この度は心よりお悔やみ申し上げます。」という言い回しが一般的です。「ご愁傷様です」と併用し「この度はご愁傷さまです。心よりお悔やみ申し上げます」と伝える場合もあります。
ご愁傷さまです
「ご愁傷様です」は「愁傷」という言葉に敬語表現を加えたものです。愁傷は心の傷を憂うという意味があり、お悔やみの挨拶では、お悔やみ申し上げますと並んでよく使われる言葉です。
弔電の文中にも使用できますが、「ご愁傷様です」は話し言葉として使われているため、あまり親しくない方には不適切となってしまいます。弔電で使用する場合は「お悔やみ申し上げます」が無難です。
また、「お悔やみ申し上げます」や「ご愁傷様です」に似た言葉として「哀悼の意を表します」や「ご冥福をお祈りします」があります。これら2つの言葉は口語体ではないため、直接口頭で伝える際には使わないようにしましょう。書き言葉なので弔電の文中には使っても構いません。
<よく使われるお悔やみの挨拶の文例>
|
| 葬儀の服装については以下の記事で詳しく解説しております。 葬儀で失礼に当たらない服装とは?押さえたいマナーと注意点 |
お悔やみの挨拶の文例【状況別】
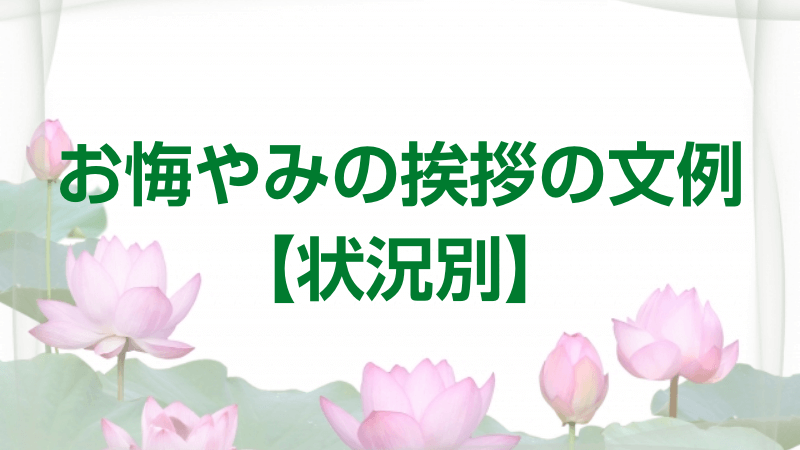
お悔やみの挨拶をする際、どのように挨拶すればよいのかわからず不安に感じる方もいることでしょう。状況別に、お悔やみの挨拶の文例を紹介します。
訃報を受け取ったとき
訃報を受け取ったときは、失意の中でも連絡をしてくれたことに対する感謝を述べるようにしましょう。同時に、通夜や葬儀の日程確認も行っておくことをおすすめします。
<訃報を受け取ったときに使うお悔やみの挨拶の文例>
|
受付で挨拶をするとき
葬儀の受付では、基本的にお悔やみの挨拶をするのがマナーです。一般的なお悔やみの挨拶と大きな違いはありませんが、お香典を渡す場合は「ご霊前にお供えください」という言葉を付け加えるようにしましょう。
<受付で使うお悔やみの挨拶の文例>
|
キリスト教葬儀の場合
宗教によって「死」に対する考え方が異なるため、仏教とキリスト教ではお悔やみの挨拶が異なります。
仏教における「死」は「人生の終わり」を意味しますが、キリスト教は「死」を悲しいものとは捉えていないため、「お悔やみ」や「ご冥福」といった言葉は用いないのです。特に「ご冥福」は仏教用語のため、キリスト教葬儀の場合は使うべきではありません。
仏式のような文言は避け、「安らかに」や「お祈りします」といった言葉を使うようにしましょう。
<キリスト教葬儀におけるお悔やみの挨拶の文例>
|
| 葬儀の香典の書き方については以下の記事で詳しく解説しております。 【どこまで知ってる?】葬儀の香典の書き方|宗教ごとの違いや連名の書き方まで |
お悔やみの挨拶は状況によってメールで伝えても良い

お悔やみの挨拶は基本的には直接口頭で伝えるべきですが、状況によってはメールで伝えても大丈夫です。直接伺うことがどうしても出来ない場合、どうすればいいのか迷うのではなく、メールですぐにメッセージを送りましょう。
ただし、メールでお悔やみの挨拶をする際もマナーはあるため、どのような場合ならメールで伝えても良いのか、メールで挨拶をする際のマナーとともに紹介します。
メールでお悔やみの挨拶を伝えても良い場合
メールでお悔やみの挨拶を伝えても良いかの判断は、相手との関係性によります。親しい友人や知人、同僚の場合はメールで伝えても問題ありません。
ただし、本来お悔やみの言葉は直接伝えるのがマナーです。親しい間柄だったとしても、形式や慣例を重んじる人や目上の人に対してメールで伝えるのは避けたほうが無難でしょう。
メールでお悔やみの挨拶をする際のマナー
メールでお悔やみの挨拶をする際は、文章はなるべく簡潔にまとめましょう。
長文でお悔やみの挨拶をしたほうが丁寧なのではと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、親族を失ったご遺族は葬儀の手配などをしなければならないため、多忙である場合がほとんどです。多忙な相手に長文の挨拶をしても却って迷惑なため、簡潔な挨拶が適しています。
文章だけでなく件名も要件が一目でわかるような文面にすることを心掛け、訃報を受け取った後はすぐに返事をするようにしてください。また、親しい間柄だとしてもくだけた文面でメールを送ることは絶対に避け、必ず敬語や丁寧語を使いましょう。直接伝える場合と同様に重ね言葉や忌み言葉も厳禁です。
メールで伝えるお悔やみの挨拶の文例
最後に、お悔やみメールの文例を、送る相手ごとに紹介します。
メールでお悔やみの挨拶をする際の参考にしていただければ幸いです。
<友人など親しい間柄の人に送る場合>
| 【件名】△△(送り主の名前)より お悔やみ申し上げます 【本文】お母様の訃報をお聞きし、大変驚いています。遠方のため駆けつけられず、メールでの連絡になってしまい誠に申し訳ございません。大変だと思いますが、どうか無理せず自身の身体をいたわってください。私にできることがあれば、いつでもご連絡ください。どうかお力を落とされませんように。 |
<会社の上司や同僚に送る場合>
| 【件名】△△(送り主の名前)です お悔やみ申し上げます 【本文】この度は逝去の報に接し、心からお悔やみ申し上げます。ご家族を支えなければと無理をされていないか心配です。どうか気を落とさず、お身体に気をつけてください。本来であれば直接ご弔問に伺うべきなのですが、遠方のためままならず、申し訳ございません。書中にて、心よりご冥福をお祈りいたします。 |
<取引先などビジネス関係の人に送る場合>
| 【件名】株式会社〇〇 △△(送り主の名前)より お悔やみ申し上げます 【本文】お身内にご不幸がおありだったと伺い、大変驚いております。本来であれば直接お悔やみを申し上げるべきなのですが、遠方のためメールとなり申し訳ございません。返信のお気遣いは不要です。心から哀悼の意を表します。 |
| 葬儀時のバッグについては以下の記事で詳しく解説しております。 葬儀にふさわしいバッグとは?マナーや選び方について詳しく解説 |
基本的な知識を押さえて、誠意のあるお悔やみの挨拶を
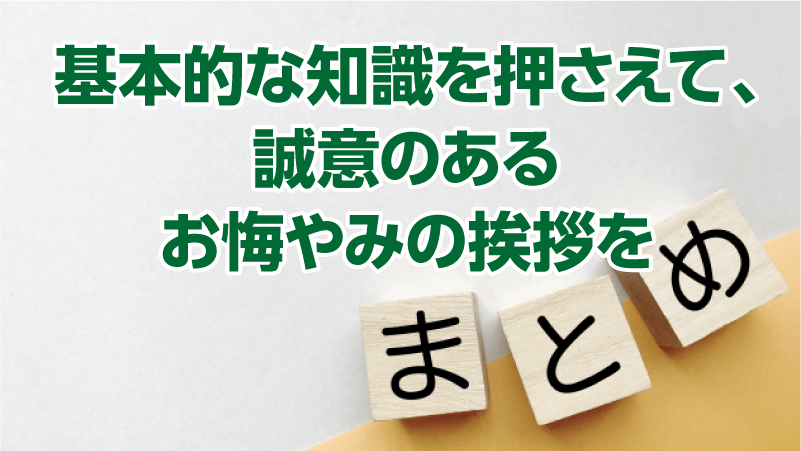
今回の記事では、葬儀でのお悔やみの挨拶について、基本的なマナーや状況別の文例を紹介しました。基本的なマナーを把握せずにお悔やみの挨拶をしてしまうと、ご遺族に対して失礼にあたる場合があります。
しかし、あまり神経質になりすぎる必要もありません。何よりも重要なのはご遺族への思いやりです。基本的な知識を押さえて、誠意のあるお悔やみの挨拶ができるようにしておきましょう。